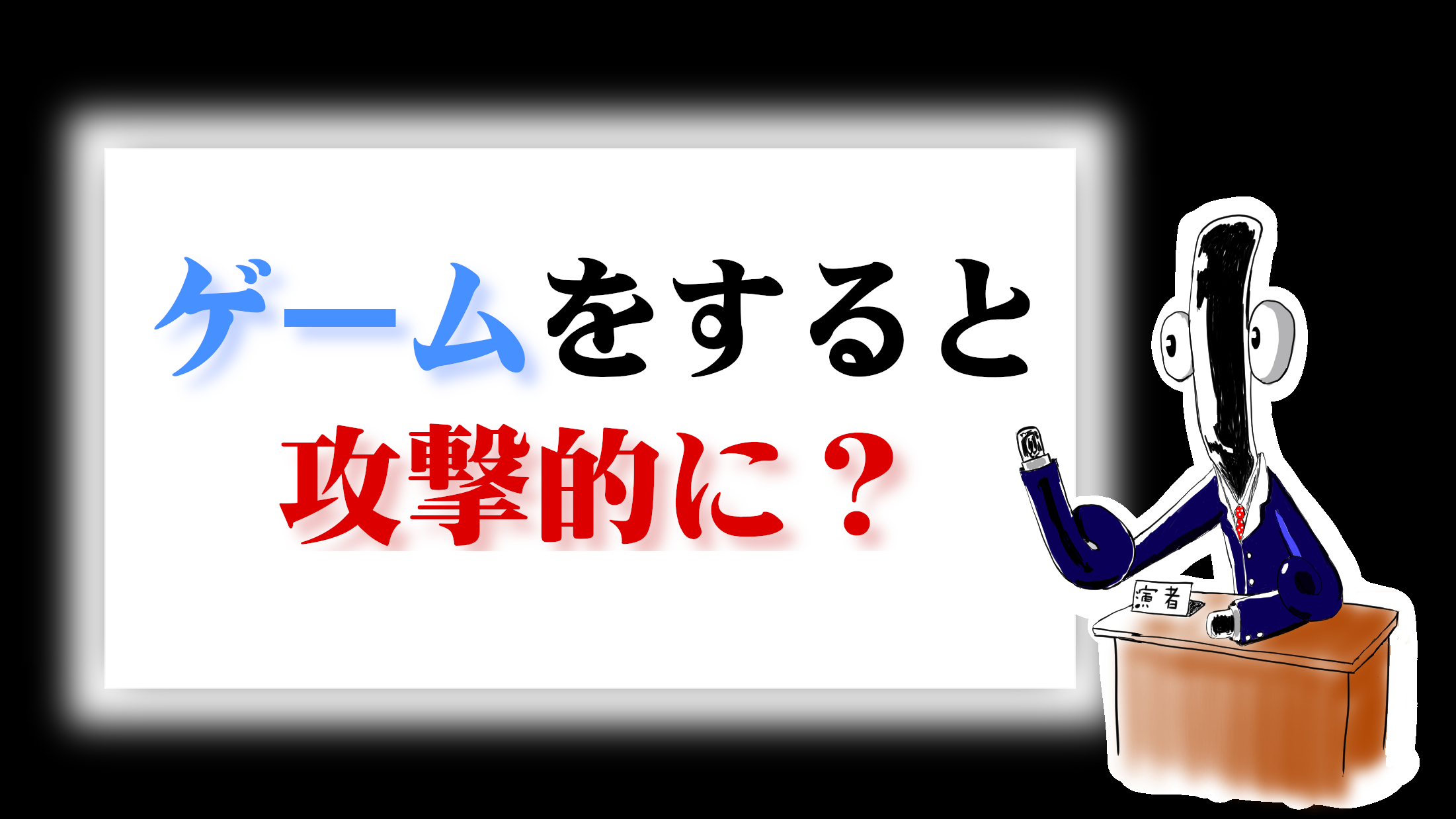
2019年1月26日、朝日新聞に「ゲーム依存は、病気です」という見出しで、紙面を大々的に使ってゲーム依存に関する記事が書かれていました。
スマホやゲームの依存の低年齢化と、「ゲーム障害」がWHOの国際疾病に認定されたことを中心に、現代の日本で起きている問題について様々な事象を取り上げて説明していました。
このような記事が出ることは、別記事「ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本のレビュー」より想定内と言ったところですね。
記事の内容については、僕もおおむね賛成です。若年層の依存症が増えている問題は、警鐘を鳴らす必要があると思います。
ただし、この記事で用いられている説明のうち次の2点が気になったので、それについて取り上げたいと思います。
- 脳が攻撃的に?
- ネット依存患者の脳
本記事では5つの論文を紹介します。結論だけ知りたい方は[1-まとめ]、[2]だけ読むことをおすすめします。
脳が攻撃的に
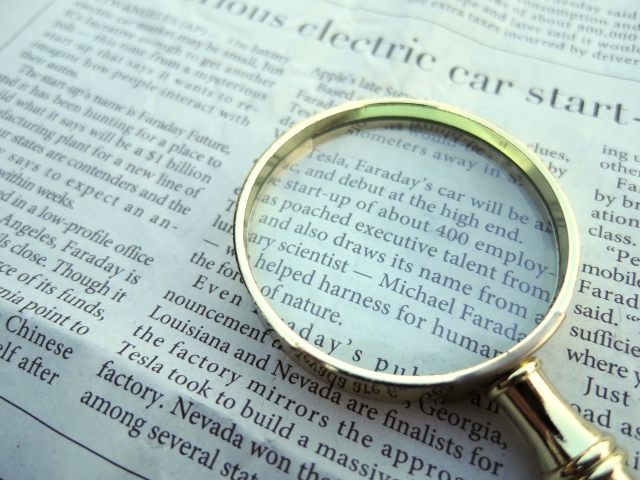
新聞の中見出し「脳が攻撃的に 睡眠障害も深刻」の中に気になる文がありました。
具体的な文章を、以下に引用します。
暴力的なゲームを長時間続けたり、刺激的な映像を長時間見続けたりすると、他人の痛みを感じる脳の中枢は鈍く、自らの痛みを感じる中枢は過敏に反応して攻撃的になること、また、低年齢ほど依存性になりやすく、回復に時間がかかることも確認されている。
<引用:2019年1月26日朝日新聞より>
前置きとして、「暴力的なゲームをすると攻撃的になるか」という疑問については、以前の記事「ゲームの悪影響について調べてみた」で調べたところ、ほとんど影響がないという見解が得られました。
ですので、この記事の内容に驚いたのと、記事の元にした文献を調べてみたいと思いました。
まず、この記事では脳の働きについて述べられているので、『「脳科学や医学」の話かな?』と予想しました。以前の調査はあくまで、「心理学」的な研究の結果なので、別の分野では異なる結果が出ていてもおかしくないだろうと思います。
それで調べてみた結果から言ってしまうと、論文見つかりませんでした…
「violent(暴力的な),video game(ビデオゲーム),brain(脳),aggressive(攻撃的),fMRI*(磁気共鳴機能画像法)」などをキーワードにして探してみたのですが、それらしい文献は見当たらず…
だからと言って、この記事がデマというわけではなく、よくよく探せば元となった文献はあるんだと思いますが、引用元が分からないので仕方がないですね。
その代わり、引用元を探しているうちにいろいろな論文に目を通し、この文に対して意見を言えそうな結果が得られたので紹介します。
~調査結果~
本記事では5つの文献を使って考えていきたいと思います。

1.インターネットゲーム障害の脳画像研究に関する最新の概観
この文献はまさにIGD(インターネットゲーム障害)について脳画像研究の結果をまとめたものになるので、これさえ押さえておけば、IGDについて現在どのような見解がされているのか把握できます。
本文献によると
・最近の機能的磁気共鳴画像法研究は、IGDである思春期および成人患者の”注意”、”運動協調性”、”実行機能”および”知覚”に関連する脳の領域において灰白質(およそ脳の表面に位置する部位)の体積が減少していたことを示した。
これを皮切りに、さまざまな悪影響について書かれていますがそのうち本件に関係するのが次の点です。
・感覚の伝達を司る領域の接続性に異常が見られた。
・ICDは薬物中毒症の特徴を示す。
これが本当であれば、痛みを感じる機能が変化したり、薬物中毒と同様の性質がみられてもおかしくないような気がします。
2.自発的脳活動は攻撃性について暴力的なビデオゲームの影響を示さなかった:安静時fMRI研究
タイトルから分かる通りこの論文は暴力的なビデオゲームが攻撃性に関係していることを否定しています。
まず「自発的脳活動って何?」と思うんじゃないでしょうか。今までの研究ではビデオゲームの影響をfMRIで調べるときは、検査中に感情を刺激したり、情報を与えたりするテストを行いながらMRIの検査を行っています。それに対してこの研究は、MRIの検査中に何も考えないようにしています。その「何も考えない=安静状態」の脳活動が自発的脳活動であり、それを調べることで潜在的な脳活動へのビデオゲームの影響を調べることができるというわけです。
ではでは、研究結果です。
暴力的なビデオゲームに長時間さらされても自発的な脳活動、特に実行制御、道徳的判断および短期記憶などの中枢脳領域に大きな影響はないことが分かった。
これまでの研究は暴力的なビデオゲームの悪影響が誇張されている。
また、討論(discussion)の部分が激しく同意だったため記載させていただきます。
攻撃性の原因を単純に明らかにできない。なぜなら、子供のころのトラウマ、家族の経歴など多くの環境要因が、相互的に攻撃性に関与しているため。
個人は「白紙の人間」ではなく、個性を持っている。暴力的なビデオゲームを選ぶ動機が異なると結果が異なる可能性があることが証明されている。動機はストレス解消目的か、暴力享受目的かといった。
これは、以前の記事で書いたゲームの悪影響についての研究の問題点と同じで、納得の意見です。やっぱり“攻撃性”はビデオゲームの影響より個人の問題の影響が大きいんじゃないでしょうか。
この論文は、2018年に掲載されており、論文1.「IGDの概観」よりも後に報告されていることから、これまでのゲームと攻撃性の関係を主張するこれまでの論文を踏まえたものであり有力と考えます。
3.暴力的なビデオゲームに長時間触れることは痛みに対する共感性の減少を示さない:fMRI研究
タイトルに「長時間」、「ビデオゲーム」、「痛み」、「共感」というキーワードがあるので、なかなか探していた文献に近そうな内容ですね。
研究方法
ビデオゲームの経験をアンケート調査。痛みの表現が含まれる画像と含まれない画像を見る。fMRI検査。
結果
暴力的なビデオゲームをするグループと非暴力的なビデオゲームをするグループのfMRI上の知覚は有意差がなかった(違いがあるとは言えない)。
この論文を信用すれば、朝日新聞の記事は間違っていることになりますが、どちらの結果もあると判断した方が良いんだと思います。
この論文も2017年に掲載されたものであり、比較的新しいものであることから信頼性はあると思います。
4.暴力にさらされると他人の痛みに対する共感反応が減少する
朝日新聞の記事が「暴力的なビデオゲームを続けたり、刺激的な映像を見続けたり」と並列的に書いているので、元ネタはビデオゲームじゃなくて暴力メディア全般の研究なのかなと考えてビデオゲーム以外の研究も調べてみました。
研究方法
参加者に暴力的または非暴力的なビデオを5分間見せる。その後痛みの表現が含まれる画像を見せる。fMRI検査。
結果
他人の痛みへの共感反応が減少した。
5分間のメディアの暴力への曝露は、痛みに対する共感に短期間の影響しか及ぼさない可能性がある。
この結果は朝日新聞の記事を一部裏付けるものとなりますが、短時間のメディアの暴力表現が短期間の影響しか及ぼさないとしたらあまり深刻に受け止める必要は無さそうです。
だいたいこの論文だけの問題ではありませんが、暴力表現を見た後にMRI検査を行ったとしたら、不安や恐怖の精神状態になっているから他人の痛みに共感できる精神状態じゃなくても全然不思議じゃないですよね。
5.ゲーマーの感覚が鈍くなるという神話:非ゲーマーに関する長期的fMRI研究において暴力的なビデオゲームのプレイ後に痛みへの共感が薄くなる証拠はない
この研究では、これまでの研究は横断的*1だったのに対して、それではビデオゲームと共感の低下の因果関係が分からないということで縦断的*2手法で行われています。
要は、『1回きりじゃなくて長期間継続的に影響を見ないと因果関係なんて分からないでしょ!』ということです。
研究方法
参加者を暴力的なビデオゲーム「Grand Theft Auto 5」をする人と社会生活シミュレーションゲーム「The Sims 3」をする人にランダムに割り当てる。痛みの表現が含まれるおよび含まれない写真またはビデオゲーム風の画像を見ながらfMRI検査を行う。調査期間は16週に渡って行われる。
結果
暴力的なビデオゲームをするグループの痛みに対する共感神経ネットワークの感度低下の証拠は見つからなかった。
縦断的に調査しても共感の低下が見られなかったので、やはり暴力的なビデオゲームが痛みの共感を低下させるというのは誤りである可能性が高いということでしょう。
この論文は2018年に掲載。論文3.と同様にこれまでの報告を否定する結果となりました。また、論文2.のように従来の手法の問題点を改めて検証することで、より正確な結果を得ることを目指した研究です。
まとめ
暴力的なビデオゲームによる攻撃性の増加と、痛みの共感の低下はこれまで報告されてきたが、
長時間暴力的なビデオゲームをしても、潜在的に暴力的にはなるとは言えない。また痛みの共感が低下するとも言えない。という証拠がある。
よって、朝日新聞の記事は情報源が分からない以上間違いとは言えないが、正しいとも言えないということになります。
個人的な意見ですが、長時間ゲームをするIGD患者の特徴をIGD患者だけじゃなく長時間ゲームをする全ての人に当てはめようとするから混乱が生じるのだと思います。この問題のそもそもの発端はインターネットゲーム依存によって、日常生活に大きく支障をきたすような中毒者が現れ始めたことです。それを防ぐためにWHOがIGDの対策に動き始めました。
ビデオゲームの悪影響については、いまだ激しい議論がされています。
『IGD患者が生まれるのは、ゲームに根本的な悪影響があるからに違いない!』と考えるのは早計かなと思います。『IGDになる人を取り巻く”環境”という外的要因によって、インターネットゲームに依存する状況が作り上げられる』という考え方も重要ではないでしょうか。
ネット依存患者の脳
2つ目の衝撃を受けたこと。
ネット依存になると神経細胞が破壊され、脳が萎縮する!
記事の中に「ネット依存患者の脳」ということで、Yuanらが報告した脳のMRI画像が掲載されていました。下記にリンクを貼りますので興味のある方は見てみてください。
新聞記事では暗闇でゲームをする人たちの写ったおどろおどろしい背景で説明されています。”THE現代社会の闇”って感じです。
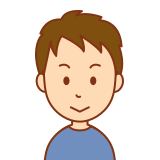
これはビビります。
と言いつつ、こういう記事はソースが気になるので、論文を探してみました。こちらの方は研究者の名前が書かれていたので、すぐに見つけることができました。
論文では長期のインターネット中毒が脳の構造変化をもたらすことを示唆した。とあります。
これもインターネットをするとそうなると言うより、中毒になると起きると考えた方が良いのでしょう。
僕の勝手な想像ですが、脳の特定の回路だけが集中的に強化されて、その反面使われなくなってしまった脳の部分が衰えるとかですかね。
ゲーム障害の論文にもありましたが、インターネットゲーム障害になると薬物中毒と同じような症状を示すと報告されているので、脳の変化に関しても同じような状態になるのだと思います。
ちょっと詳しい話をすると、私たちに気持ちよさをもたらす一般的な物質が「ドーパミン」と呼ばれる神経伝達物質です。通常はドーパミンが過剰に分泌されないように抑制性ニューロンと言う神経細胞が働いているのですが、アルコールなどの依存性物質を摂取すると抑制性ニューロンの働きが阻害されてしまいます。
<参考>脳とニューロン.『ニュートン』別冊
この悪循環により依存がどんどん進行していきます。ただ、インターネットやゲームはもちろん依存性物質ではないので、このメカニズムをそのままは適用できません。
あくまで素人の妄想ですが、インターネットやゲームは快感を得やすいことは事実だと思います。それがドーパミンの過剰分泌につながることや、ストレスなどの外的要因によって脳の機能が損なわれることが引き金になって依存症が起きるのかなと想像してみたり。
依存症のメカニズムについても研究されているが、はっきりしたことは分かっていないと言うのが現状のようです。
さいごに
暴力的なゲームと攻撃性の関係について反論しましたが、依存症になった場合の悪影響については否定しません。
ゲームもネットも「好きでやっている」から、「やらないと気が済まない」になると危ないと思います。
それを防ぐために、ゲームもネットも自分で使う量と時間をコントロールできるように意識していくことが今後大事なのではないでしょうか。
【参考文献】
1.インターネットゲーム障害の脳画像研究に関する最新の概観
WEINSTEIN, Aviv M. An update overview on brain imaging studies of Internet gaming disorder. Frontiers in psychiatry, 2017, 8: 185.
2.自発的脳活動は攻撃性について暴力的なビデオゲームの影響を示さなかった:安静時fMRI研究
PAN, Wei, et al. Spontaneous brain activity did not show the effect of violent video games on aggression: a resting-state fMRI study. Frontiers in psychology, 2018, 8: 2219.
3.暴力的なビデオゲームに長時間触れることは痛みに対する共感性の減少を示さない:fMRI研究
GAO, Xuemei, et al. Long-time exposure to violent video games does not show desensitization on empathy for pain: an fMRI study. Frontiers in psychology, 2017, 8: 650.
4.暴力にさらされると他人の痛みに対する共感反応が減少する
GUO, Xiuyan, et al. Exposure to violence reduces empathetic responses to other’s pain. Brain and cognition, 2013, 82.2: 187-191.
5.ゲーマーの感覚が鈍くなるという神話:非ゲーマーに関する長期的fMRI研究において暴力的なビデオゲームのプレイ後に痛みへの共感が薄くなる証拠はない
KÜHN, Simone, et al. The myth of blunted gamers: no evidence for desensitization in empathy for pain after a violent video game intervention in a longitudinal fMRI study on non-gamers. Neurosignals, 2018, 26.1: 22-30.
<関連記事>





